

|
  |
 |
  |
![]()

![]()

昔、潮風が薫る街が、今、サツカーの街に変わろうとしている。
残念ながら、サッカーの街になるには、まだまだです。
ジェフ市原の姉崎練習場には毎日全国から選手の応援にきています。
ジェフ市原のファンを一人でも多くして、臨海競技場をいっぱいにしたい。
ジェフが市原市を全国区にしてくれました。ありがたいことです。
姉崎の絵葉書の紹介を下記にてしています。

また、宝生堂が日頃ご贔屓にして戴いていますお客様のサイト
姉崎の郷土史、史跡の紹介が年代別にわかりやすく紹介されているお奨めサイト
![]()
 |
 |
 |
 |
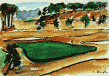 |
| 京葉工業地帯 | 妙経寺 | 姉ヶ崎駅 | 姉埼神社 | 姉崎カントリー |
市原市姉崎は、古墳時代、豪族である上海上国造の本拠地として栄え、大型古墳の二子塚、天神山古墳
などを含む古墳群は、千葉県を代表するものであり、その中に位置する式内姉埼神社も創建がそのころです。
椎津にあります通称城山は、中世の城跡で、木更津の真里谷に本拠地をおいた武田氏が、交通の要衝であり
峻嶮な要害地である椎津に、真里谷本城の北の守りとして築城したといわれています。椎津城主武田政信は
房州の里見氏との激戦の末大敗し、その後、結城秀康の次男松平忠昌、三男直政がこの地を治め、江戸時代末
までは、水野忠詔が、安房国北条より椎津の現姉崎小学校の地に城(陣屋)を移し、藩校「修来館」を有する
文武に名高い鶴牧藩一万五千石を治めていました
.明治45年開業した姉ケ崎駅(宝生堂の創業もこのころ)に程近い顕本法華宗妙経寺は

、儀僕市兵衛、孝子五郎、鶴牧藩の上代家老手嶋家、藩士の墓があり、(当家榊原も藩士)
水戸光圀が宿泊した記録も残る古刹としてしられています。
大型の木造船、五大力船により古くから江戸との交流も盛んで、数多くの物や人、文化が行き交いました。
どこまでも続く遠浅の海は、海水浴、潮干狩り、すだて 、納涼などの娯楽、海苔の養殖、海老、シャコ、貝などの
、納涼などの娯楽、海苔の養殖、海老、シャコ、貝などの
各種漁業により、たいへんな賑わいをみせていました。市原市でも最初のゴルフ場、姉崎カントリー倶楽部もオープンし
姉崎音頭、姉崎踊り、姉崎ワルツ、などのご当地ソングもつくられました。
昭和30年代の京葉臨海工業地帯造成に伴い、姉崎の海も昭和36年には完全になくなり、(汐風はおほらなくなり)
京葉コクビナートの中枢を担う様になりました。東京から50キロ圏内のベッドタウンとしても発展し、山林ゃ田畑は
住宅や商店へと姿を変え、今日ジェフ市原の練習場が..サッカーの街に変われる?...つづく
絵葉書の説明はこれくらいですが、これから姉崎について下記の順に記していきます。
歴史家、では無く一般人ですので、軽く読んでください。
間違っていたら連絡ください、訂正致します。
参考文献は当家にある書物を参考にしています。
また、小出君の姉崎不思議発見をベースにして記していきます。
ここからはじまり
姉崎の由来
.海の中から姉崎出現
どっちが正しい?あねさき..あねがさき
古代
姉埼神社と古代伝説
武士の時代
頼朝伝説と鎌倉街道
椎津城山合戦記
江戸時代
幻の姉崎藩
鶴牧藩と城下町
姉崎にきた有名人
近代
| 修来館創設者 藩主 水野忠順公 |
鶴牧版 史記評林改定主任 修来館 館長田中篤實先生 |
修来館次長 豊田一貫先生 |
直木賞受賞作 上総風土記のモデル 義僕市兵衛さん |
 |




